周知の通り、現在アメリカでは急速に保護主義(輸入品に関税をかけるなどして、自国の商品を競争から守ること)の動きが加速している。グローバル経済の先導者と目されてきたアメリカが、である。国際的な取引によって、世界全体の効用(幸福)が増加していく、そのような単純なシナリオはもはや見直される段階に来ているのだろうか?
「パレート最適」。イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱した概念である。資源が無駄なく配分された、それ以上誰の効用も犠牲にせずに誰かの効用を高められない状態をパレート最適という。
例えば、ここに一本のリンゴの木があるとしよう。「資源が無駄なく配分された」については、食べられるリンゴが、残らず配られており、余ったり捨てられたりしていない状況といえる。次に「それ以上誰の効用も犠牲にせずに誰かの効用を高められない」についてだが、ここではリンゴを他のものと交換できないので、無駄のない分配がされていれば、すでに条件を達成しているとみなしていいだろう。
ものが複数ある場合、お互いの好みに応じて所持しているものを交換することで、両者の効用を増加できる。こうした誰の効用も犠牲にせず、誰かの効用を高めることを「パレート改善」という。もちろん、誰の所有物でもないリンゴを取って効用を増加した場合もパレート改善であるし、交換によって一方の効用を増加し、もう一方は変わらない場合もパレート改善だ。
市場では、交換を繰り返すことによって、パレート改善が行われている。貨幣には、交換をより円滑にする機能があり、パレート改善に大きく寄与している。ネットショッピングなどの取引のハードルを下げる存在もパレート改善につながる。理論上は交換などによるパレート改善を繰り返すことによって、やがてはパレート改善の手段がなくなり、パレート最適に至るとされている。
パレート最適な世界が理想郷とは限らない。極端な効用の偏りがあるかもしれないし、全体の効用が最大化されているとも限らない。円滑な交換が可能になったグローバル経済にも問題があるのと同じように、パレート最適な状態にも問題が残る可能性はある。
グローバル経済はパレート最適に近いかもしれない。円滑な交換によって人々の効用は増加し、豊かな生活を実感している人も多いだろう。しかし、パレート最適な世界は平等とは限らないし、その先にあるのは、おそらくは利益の奪い合いである。そうしたゲームの過程で再びパレート最適でない状態に戻ることもあるだろう。反グローバリズムは反パレート最適であるかもしれないが、個人レベルでは合理的な選択である場合もある。結局、各々が自分にとっての最適な選択をするしかないのだ。
(オウセイ)

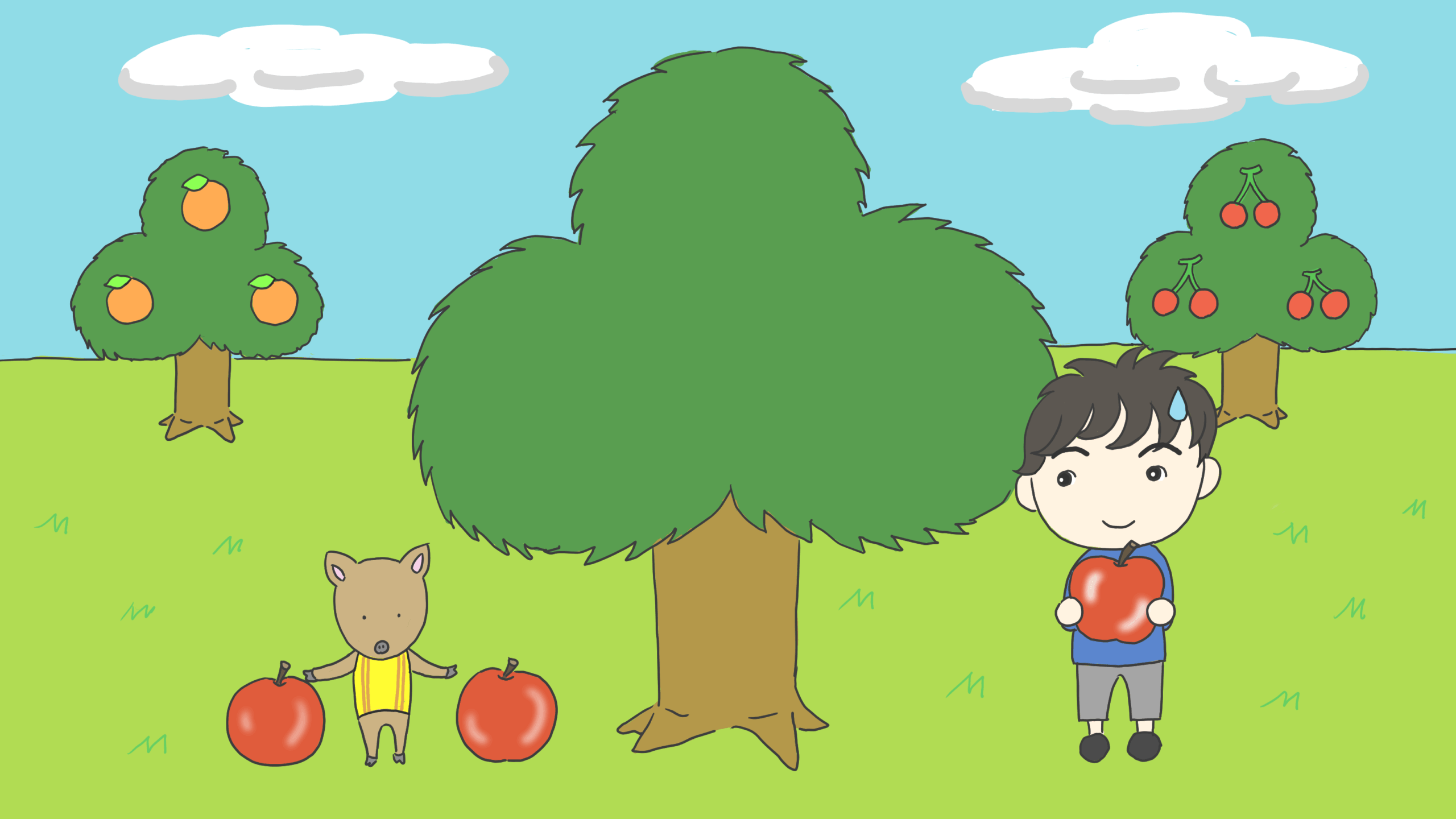
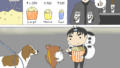

コメント