医薬品として認可してよいかの試験には大きく3つのフェーズがあり、第1フェーズは健康な若い男性を対象として当該物質をどの程度まで身体に入れても大丈夫なのか、その忍容性をみる。第2フェーズでは少数の患者さんに効くのかどうか、用量や投与間隔を変えたりしていわばアタリをつける。そして第3フェーズの、いよいよ最終テストでは既存治療とガチンコで比べて新薬候補が勝利することを求める。
簡単にいえばこうした順番でエビデンスを獲得していくのであるが、これが経済学や社会学分野ではなかなか同じようにはいかないのである。例えば先般のパンデミックに際しては、都市閉鎖がいいのか、それともしない方がいいのか、あるいは入国規制を厳格にするのか、ワクチンの接種は何回がよいのか、と、色々知りたいことはあったにせよ、医薬品と同様のアプローチが出来たのはせいぜいワクチンの接種回数くらいである。それ以外は、たとえば東京だけ都市封鎖して、大阪は都市封鎖しない、といったようなことが社会実験としてなかなかうまくデザイン出来ないのである。
同じようにして、子供には読書を半ば強制させるのがいいかとか、習い事をさせると将来の稼ぎが増えるかどうかという研究も簡単にはデザイン出来ない。運よく国や自治体がお金を出して医薬品の最終テストと同じような無作為化二重盲検のそれと同様なデザインを行えることも中にはあり、これをEBPM( Evidence-Based Policy Makinig )と言ったりもするのだが、こうした“実験”が出来るケースは限定的である。
そこでよく使われる“実験もどき”が自然実験と呼称されるアプローチである。実際には人が介入したりはしないのであるが、偶然にもフェアに比較できる状況を見つけこれを利用する。例えば、70歳以上の人は医療費の自己負担が69歳までの3割負担から2割負担に緩和されるのだが、それによって病院に行く確率はあがるのか、それとも全然かわらないのかを知りたくなったとしよう。直観的にはこれを調べるためには0歳~69歳までの人と、70歳以上の人とを比べれば済みそうな気がしないでもないのだが、これはうまくない。加齢とともにそもそも病気になる可能性は高まるのであるし、日本では75歳以上は1割負担ということもある。
自然実験はこのようにマスで全ての人を研究対象としたりはしない。例えば、69歳10か月~11か月の人と、70歳0か月~2か月の人とを比べるのである。こうすることで前述したような、比較するうえでのアンフェアさは気にならなくなり、純粋に医療費負担3割群と、医療費負担2割群との比較“実験”のような状況として切り取ることが出来るというわけである。
同様にして、例えば大学での授業や学びの機会が生涯獲得賃金を高めるのか、それとも賃金自体にはあまり違いがないのかを知りたかったとしよう。一般的には大卒の障害獲得賃金は高卒よりも高いという統計結果は出ているものの、もしかしたらこれは単なるネームバリュー、端的にいえば大学のブランドが以降の就職や昇格の機会をあげているだけで、実は大学の授業内容、コンテンツは少なくとも生涯獲得賃金に対しては何ら影響がない可能性がある。
これを調べるうえでは例えば「東京大学に入学した人」と比べる対象として相応しいのはその他の全ての人や、その他の大学に入学した人では宜しくない。授業のコンテンツ価値を調べるのであれば、「東京大学を受験し落ちた人」がより相応しい。さらに入学試験の点数を閲覧できる権限があるならば、ギリギリ落ちた人とギリギリ合格した人が、「東京大学の授業・カリキュラムの価値はあるのか」を調べるうえでは、もっともフェアな比較となる。
実際のところ、このような大学でのカリキュラム価値があるかないかという自然実験はしばしば実施されており、その結論としては「違いがない」ことが幾度も確認されている。端的にいえば、同じくらいの偏差値なのであれば、当該の大学に合格しようが不合格であろうが、以降に獲得する生涯賃金には違いがない、ということである。大学の先生はこの結果を受けて不快かもしれない。ただこれはその不合格であった学生が入学した別の大学でのカリキュラムと大きな差異がなかったというだけであって、決して無価値な授業を提供していたという結論ではないので、それほどガッカリするようなお話ではないだろう。
以上

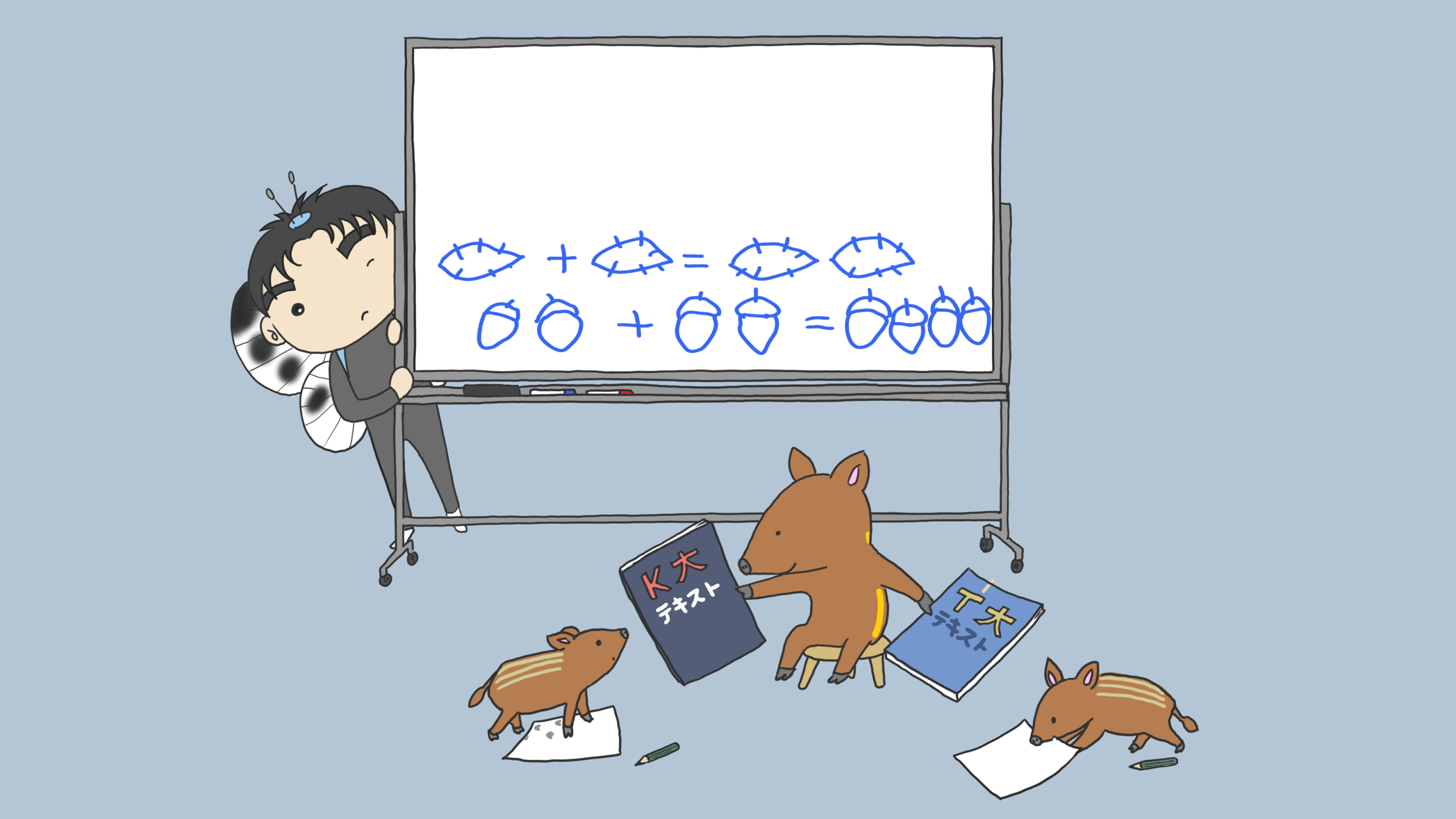


コメント