各地でクマの出没が相次いでいる。地球温暖化のあおりを受け森ではエサにありつけないとなったクマは人里に降りてきてエサを探す。クマの立場で考えると人里に降りてきたクマに対して、あるいは人に危害を加えたクマでさえ「殺すのはかわいそうだ」論も、理屈には合う。
都会の喧騒に疲れたということだけでもないのだが、昨年からセカンドハウスとして滋賀県にも家を買い、度々そこで暮らすようになった我が家なのであるが、家を買った理由は自然が豊かであったことも大きい。それ故ということでもないのだが、ネット上にあった「クマ出没マップ」をみると、隣の駅辺りでクマが目撃されている。東京で暮らす分には一生、クマに出くわさないようにも思えるのだが、滋賀と東京を往来する今の暮らしであれば、ひょっとしてひょっとするかもしれない。怖い。
クマほどには攻撃性も無さそうではあるが、ゾウなども人を襲うことはあるらしい。特にサーカスなどではゾウは人気者でお客さんを呼び込める目玉として玉乗りなどの芸を見せるが、果たして人は危険じゃないのか、なんてことを想像したりする。
何より、何故にゾウや動物たちがサーカス団から逃げ出さないのかは不思議に思っていたのだが、逃げ出さないための策として動物たちに「学習性無力感」を浸透させると聞いて、なるほどと思ったところである。
学習性無力感とは要するに「無力である」ということを学ぶということである。サーカス団に連れてこられた初日のゾウは、やはり大暴れするらしく、ロープで後ろ足をきつく縛りそれを柱などにつなぐことで逃げ出さなくさせる。2日目も3日目も同様である。ただ違うのは2日目は初日よりも、3日目は2日目よりも逃げ出そうと暴れることがだんだんと減ってくるのである。何日か経つと「暴れても逃げられない」と学習する、というわけだ。
そうなってしまえばとりあえずロープは後ろ足にきつく縛るだけで、柱につながなくてもゾウは逃げなくなる。やがてロープで縛ること自体をしなくても学習性無力感を植え付けられたゾウはもう逃げないのだそうだ。
なんだかちょっと悲しい話だ。私たち人間もこの学習性無力感を抱えて生きている生き物であることを痛感しているから余計に悲しい。毒親に育てられた子供は毒親には抵抗したりしないだろう。いじめを受けた子供はどうだろう。怖い野球監督、怖い上司。無抵抗に傷つけられ続けている人はとても少数とは言えまい。
8月になるとよく「戦後」という言葉を耳にする。第二次世界大戦が終わった、と日本で認識されているのが8月だからである。
この「戦後」という言葉は他国にもあるようだが、日本人が認識しているところの「戦前」と「戦後」という二極化というニュアンスではないという。「いちばん最近あった戦争が終わったそのあと」ということなのだそうで、もしもまた戦争が当該国で起きてしまったら、あらたな「戦後」が戦争を経てまた訪れるということである。
日本はよく平和ボケと揶揄される。「戦後」というニュアンスは戦争なるものが過去のことであって、いまは永遠の平和が訪れたと思い違いをしているのかもしれない。人類の歴史にあって人の命の奪い合いが途絶えたことはないと聞く。世界を見渡すといかに日本の「戦後」という言葉が平和ボケなのかというのが見え隠れする。
それにしても、どんなに多くの悲劇が起きそれが伝承されても、何故に戦争は無くならないのだろうか。子供にそれを聞かれてもうまく答えることが出来る親はいるのだろうか。私たちに出来ることは何だろうか。自身の無力を再認識し、その素地としてまたそこに「学習性無力感」をみるのである。
以上

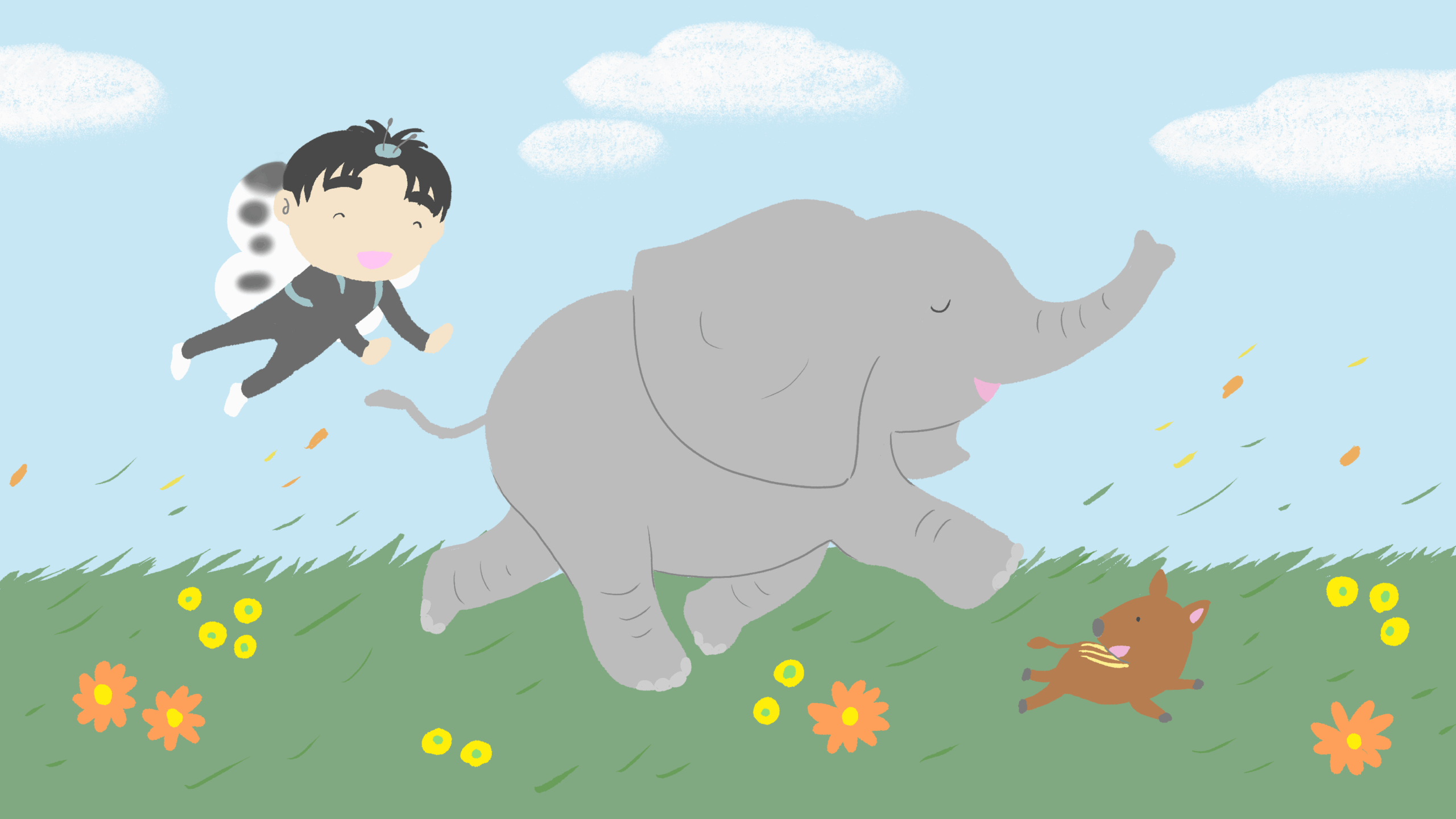
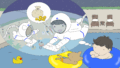

コメント