三十余年、勤務していた製薬企業を今般、退職することとなった。退職を決めたのは自分なので「退職することとなった」という言い回しもどこか他人事のようで変なのだが、数年ほど前から「そろそろ」と考えていたこともあり、あとはタイミング一つ、それが今般のタイミングになったということである。
つまり自己都合退職なのであって、一般的には会社にとっては「迷惑」ということもあろうか、退職金の3割が支給されないといったペナルティがあったりするのが日本の慣習のようではある。幸いにして“当社”は年齢等の条件が揃えば満額の支給に加え、特別加算金も頂けるという有難い制度となったばかりで、こうしたことも退職を決断するうえで背中を押してくれた気もしている。
既に業務の多くが社内業務ではなく、製薬協だとか日薬連だとかいった業界での活動にシフトしていたということもあろうか、社内の関係者が開いてくれた送別会などでは特段の感傷も何もなく、シンプルに楽しい語らいをさせて頂いたといったところである。また、コロナパンデミックの影響から、オフィス出社が毎日ではなく週に1回程度といった勤務形態となっていたこともあり既に会社への帰属意識はだいぶ薄まっていたのかもしれない。
心理学分野で語られるところの「帰属意識」とは、心理学をかじったことのない人にとっては無自覚なものであって、それが面白い。私は新潟県出身なのだが、高校野球の全国大会で母校でもない新潟代表を応援するのは何ら合理性がない。日本人が皆々、メジャーリーグで大谷選手の活躍を喜ぶのは、やはり自分と母国が同じだからということである。その際に、「これは帰属意識のなせることだなぁ」などという認識はまずないだろう。
すっかり帰属意識の薄れてしまった私であっても、やはり一緒に仕事をしてきたメンバーや、特に自分が採用に関わった人についてはこれからも頑張って欲しいという気持ちが沸いてくる。より正確には頑張って欲しいというのではなく、「幸せであって欲しい」という方がしっくりくる。仮に彼ら彼女らが会社を離れることがあってもその気持ちが変わることはないだろう。この感情は何だろう。合理性だとかそういったものがあるわけではなく、この気持ちを説明するには帰属意識という概念なくしてうまく説明がつかない。
帰属意識はよいことばかりではない。心理学が定義した「内集団びいき」とは、例えば同郷の人をひいきしたり、いま話題(?)の日本人ファースト、外国人排除みたいなこともあり難しいところである。戦争などは愛国心の存在がそれに火をつけていたりもする。案外と帰属意識が薄い方がスポーツの審判などでもフェアな判断や争いごとの仲裁も出来るものである。
社外活動が中心となっていた私は、今回の退職に際しては社外の人たちからも何度となく“卒業祝い”といったカタチでランチや夕食をご馳走して頂いたり、プレゼントなどをたくさんいただいたりした。製薬協団体への帰属意識だったり、日薬連への帰属意識だったり、こうした関係があったことを再認識させられることとなった。なんとも有難い話だ。製薬企業を退職すると同時にこうした業界団体での活動も同時に“卒業”となる。長いこと続けていた業界の薬剤疫学の促進や医療データ活用のリーダー職も今回、お役御免ということである。
退職というよりも卒業という方がしっくりとくるのは責任のある仕事を降りる、肩の荷を下ろす、ということもあるのだろう。強烈なプレッシャーを感じていたということもないが、もう会議に出席したり、あるいは会議の進行をしたりしなければならないということもない。
尾崎豊さんの「卒業」という曲にある“一つだけわかっていたこと/この支配からの卒業”という歌詞が思い出される。とにかく、私は会社を卒業したのである。卒業した会社を「弊社」とか「当社」と呼ぶこともないだろうし、また許されることでもない。
以上

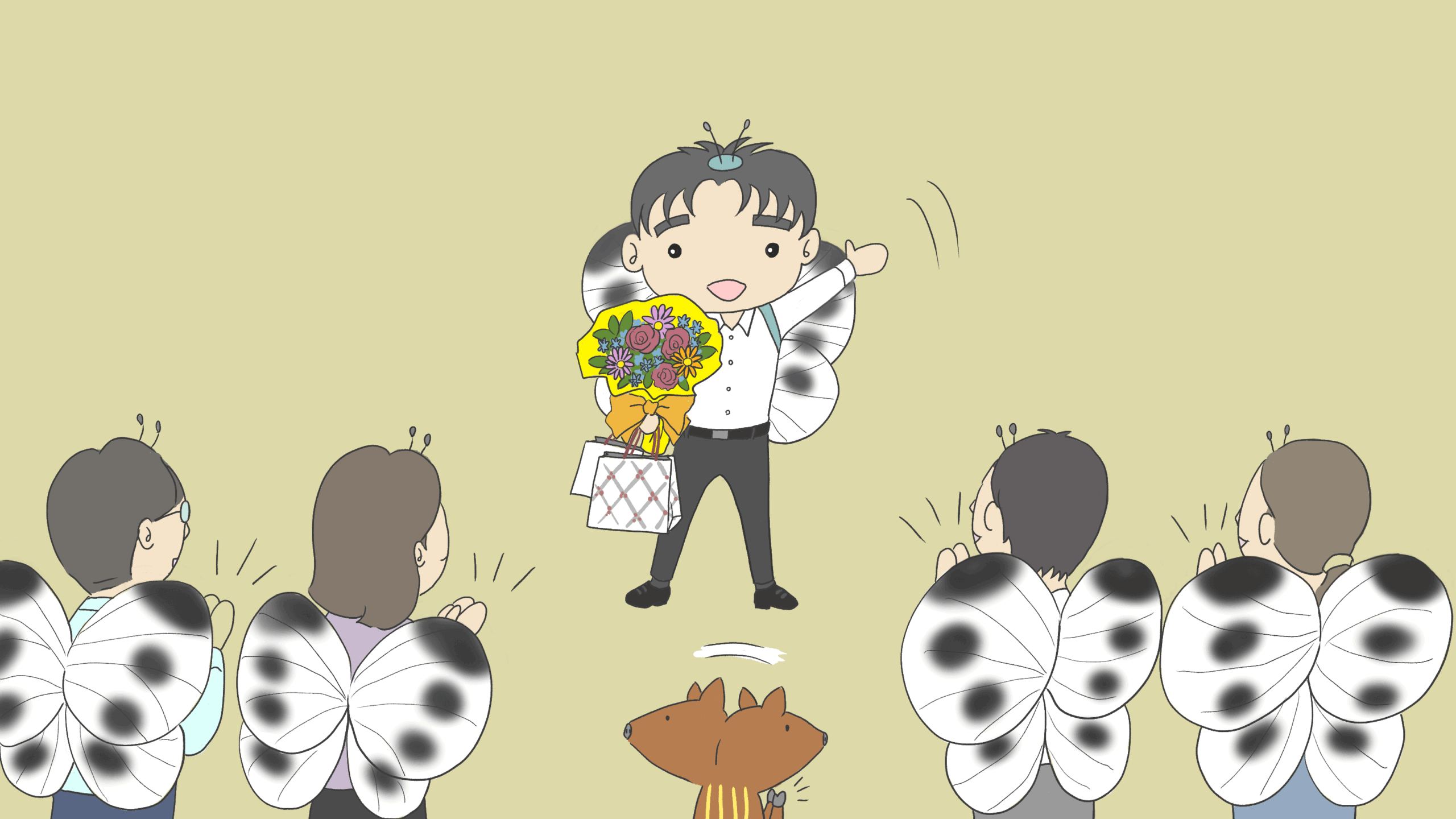
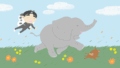

コメント