「核家族化」という言葉はもはや死語だろうか。核家族化というのは世帯の人数が減る減少のことで、私が子供の頃はよく聞いたワードである。今ではそれが解決したというのではなく、むしろ常態化したのであって一人暮らしの人は2025年現在、全体の38%にものぼるという。
私自身は10年ほど一人暮らしをしていたのであるが、むしろ親元を離れての暮らしは正直なところ快適そのものであって、あの頃がたまに懐かしくも感じられる。ただし、大学生時代のそれは一人暮らしといっても、ほぼ連日、誰か友人が家にきていたので、むしろ「はやく帰ってくれないかな」と、一人になりたいという切望をすることがしばしばあった。
いまどきの一人暮らしは「孤独」あるいは「孤立」というワードで社会問題化してきている。私のような学生の一人暮らしが問題なのではなく、高齢者の一人暮らしが問題視されているのであって、世帯数としては730万世帯であるという。つまり日本では現在、730万人の高齢者が一人暮らしをしているのである。
少し注意を払わなければならないのは「孤独」と「孤立」の違いだろう。「孤独」というのは主観であって、たくさんの集団の中に身を置いていても、あるいははた目からみたら仲の良い友人の中に身を置いていても「孤独を感じる」のであれば孤独なのである。一方で、物理的に人里離れたところに1人で住んでいるような場合は、社会的に孤立していることになる。物理的に孤立していても、自身が他者とつながっているような感覚があったり、ペットと一緒に快適に暮らしていたりしていれば孤独とは感じないだろう。
疫学の研究では特に集団の中に身を置いているにも関わらず、孤独を感じるというのは健康によくないぞという研究が知られており、疾病発生リスクベースでいえば煙草を1日15本吸うのと同じくらいだ、などとされる。それだけ孤独感というのは恐ろしいもので、直観的にわかる精神疾患だけでなく、心臓疾患等々までその発生割合は高くなってしまうのである。
具体的な数字としては、以下のような数字が文献やWeb等からみてとれる。
総死亡リスク: 14-32%上昇
心血管疾患による死亡: 29-32%上昇
冠動脈疾患の発生: 29%上昇
認知症の発症: 20%速く進行
だからといって既に不仲になったパートナーと一緒に暮らすというのはかえって不幸ともいえるだろう。そういった夫婦の場合は離婚した方が孤独感は減少する可能性が高いかもしれない。その意味で一人暮らしの数そのものを孤独の指標とするのは必ずしも適切ではないのだろう。
他方、では社会的孤立は健康に悪影響がないかといえばそうでもない。孤独を感じている、いないに関わらず孤立はうつ病と強い関連性があることが知られており、やはりヒトは古来「群れ(むれ)」で暮らす生き物だったということなのだろう。
会社を退職したタイミングで会社という「群れ」、集団に所属しなくなるという自分を俯瞰したときに、そんなことが頭の中を駆け巡ったところである。
以上

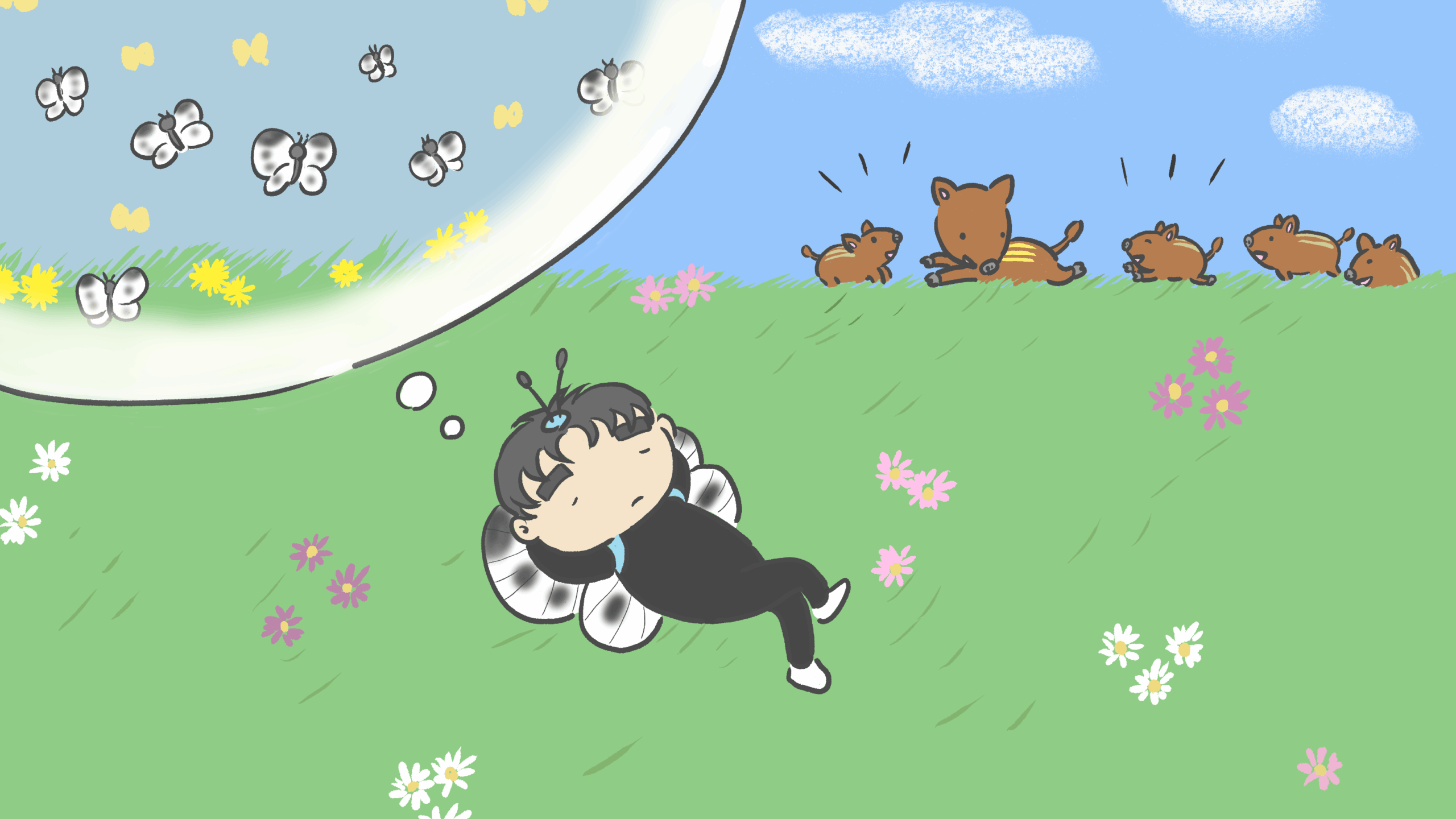

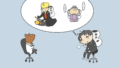
コメント