ある所にけちんぼうな侍がいて、ごはん時になるとうなぎ屋が焼くうなぎのにおいを吸い込み、それを頼りに米を食べていた。すると、うなぎを買わないその侍を快く思わない店主が彼の家にやってきて、うなぎのにおいをかぐ「かぎ賃」を払うようにいってきた。すると、侍は銭の音を鳴らして「これで銭を受け取ったことにしろ」といったらしい。
『うなぎのかぎ賃』という江戸小噺のあらすじである。近所にうなぎ屋がある方は試してみてはいかがだろうか。
取引というのは、双方に利益があって成立するものなので、うなぎを焼いて売る店主とうなぎを食べに来る客にはそれぞれ利益があるのだが、うなぎのにおいをかいだだけの第三者まで得をするのは典型的な「外部経済」といえる。
外部経済は、正の外部性とも呼ばれるもので、第三者にプラスの影響を与えるタイプの外部性である。例として、しばしば言われるのは教育の外部経済である。教育に関する投資はもちろん受けた本人の効用に寄与するが、その当人が社会全体にプラスの影響をもたらすのであれば、教育は提供者でも受けた側でもない第三者にもメリットがあるということになる。
こうした外部経済が存在するために、教育への投資は本人やその保護者だけが行うのでは過少、すなわち市場が持つ需要と供給のシステムに任せても最適な供給量が供給されないということである。こうした理屈から、政府等による教育分野への投資は正当化される。
外部経済というプラスの側面があれば、外部不経済あるいは負の外部性というダークサイドもあり、公害などはその典型的な例である。その工場を持つ企業と取引していない第三者が損をしている状況で、ここには明確な利害対立がある。
公害問題などの外部不経済を放置しておくと、今度は逆に過剰な投資が行われ、社会全体としては好ましくないことが起こってしまう。こうした事態に対しては、供給量ゼロを目指す、いわば法律で禁止してしまうこともあるだろうし、罰金のようなもので供給量を調整する場合もあるだろう。
近年では、二酸化炭素排出による地球温暖化という人類・地球規模の外部不経済が目下進行中らしいが、これに関して一つ、「自由市場」的な試みが検討されている。二酸化炭素の排出量取引である。
許可される二酸化炭素の排出量を国や企業ごとに決めて置き、各々が許可された排出量を自由に取引できるようにするというものである。つまり、二酸化炭素を出さない国(出してまで生産するメリットが薄い国)が二酸化炭素を出したい国に(出してまで生産するメリットがある国)に排出量を売ることで、全体の排出量を一定にした上で、より効率的な生産可能になるというわけだ。
企業の場合は、自国の政府という大きな力でこの試みを成功させる算段もありそうなものだが、国家間となると少し厄介で、そもそも国ごとの二酸化炭素排出量を決められるか(ルールが守られるか)という国際協調の問題になってくる。今の世界で、二酸化炭素の排出量制限という取り決めが意味を持つのかどうか、皆々様のご想像に委ねたい。
うなぎを焼く香ばしい香りから大気中の二酸化炭素まで、外部経済(外部不経済)というものは空気のように知らず知らずのうちに発生している。自由市場における「見えざる手」に任せていてはうまくいかない「市場の失敗」の一例だが、外部経済というものも一筋縄ではいかないいわば「見えないもの」というわけだ。大切なものは、目に見えない?
(オウセイ)



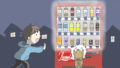
コメント