トレーディングカードゲーム、略してTCGをプレイしたことはあるだろうか?トランプなどのあらかじめ決まったカードを使って遊ぶカードゲームと異なり、自分でカードを買ったり、人と交換したりして(故にトレーディングである、おそらく)、自分用のデッキを作り、各自がそれを使って、基本的に1vs1対戦する。一時期はその需要の過熱から、高額転売などが問題となり、今なお強盗などの問題が発生している。
強力なカードを集める。購入するというのももちろんあるのだが、強さが同じでもレアなものもあったりして、コレクターにとどまらず需要がある。こういったものも「顕示的消費」に該当するのだろうか。
顕示的消費とは、周囲に顕示、簡単にいえば見せびらかすことを目的とした消費行動のことである。アメリカの経済学者ソースティン・ヴェブレン(1857~1929)が著書『有閑階級の理論』で言及した概念でヴェブレン消費ともいう。有閑階級とは、資産を多く持ち、生活のための労働が必要ない貴族のような社会階級をさしており、かつては顕示的消費の中心的な主体であった。
バッグ、時計、車などのブランド品を求める姿勢は顕示的消費の代表例である。こうしたブランド品による顕示的消費は、値段が高いほど盛んになる傾向があるとされており、値段が安いほど商品が売れる、一般的な需要の概念とは異なったものになるようだ。この現象はヴェブレン効果と呼ばれる。
近年では、裕福な人々の高級志向だけにとどまらず、消費者の様々な行動が顕示的消費として捉えられているらしい。例えば、ハイブリッド・カーやフェアトレード製品を選ぶ消費行動は、「環境に配慮している自分」を周囲にアピールする顕示的消費と見られることもあるようだ。
その他には、SNSによる発信を目的とした消費など、今日いわれる顕示的消費は多岐にわたっている。明確な階級差がなくなり、モノがあふれかえる時代の象徴とでもいったものなのだろうか?
なお、顕示的消費は経済学一般においては非合理的な行動というわけではない。結局のところどのようなことによって自分の効用(幸福)を最大化するかは人によって異なるため、各人の効用最大化という目標に関しては、顕示的消費は障害とはならないといえるだろう。
ところで、ブランドは「烙印」という意味であり、自分の家畜を他者のもの区別するために使われていたようだ。他者の消費を顕示的消費と見なすことも行き過ぎれば異なる価値観に対する烙印となるかもしれない。顕示的消費を研究対象にするのも悪くないが、前述したように効用最大化問題に限って言えば、特段非合理的な行動というわけではない。結局は各々が好きなカードを集めたり、好きなように対戦したりすればよいと思うのだが、どうだろうか?
(オウセイ)


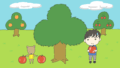
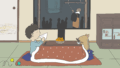
コメント